- 感応力に勝るもの
ミーターの大冒険
第一部 紫からの飛躍
第20話 本編
ジル・エフォーラム紀元博物館の中枢ホールは、時間そのものを封じ込めたかのように静まり返っていた。
高天井から落ちる淡い照明が、床に刻まれた年代軸を照らし出している。
その中央に立つ青年は、どこか現実離れした印象をまとっていた。
金色の髪。
目元に施された淡いアイシャドー。
そして、余分な力の入らない身のこなし。
――シンパシオン人。
ハニス・イザルは、ひと目でそう確信した。
「よくぞ来てくださいました」
青年は柔らかく微笑んだ。声には、訓練された抑制と、わずかな感情の揺らぎが同居している。
「以前から、あなたにお会いしたいと思っていたのです。
あなたにとっても……ミーターという――少しばかり、あのチクタクより生意気な機械にとっても、オリンさんの死は残念でした」
ハニスは思わず、鼻で短く息をついた。
「生意気なチクタク、か。
ミーターが聞いたら、湯気を出して怒るぞ」
だが、その軽口の裏で、彼は相手を観察していた。
「君がアマン・シンファーの息子だということも、すぐに分かった。
その風貌だ。シンパシオン人特有の金髪と化粧。
その身のこなし――まるで、伝説に聞くシリウス系そのものだ」
青年――ロン・シンファーは、わずかに視線を伏せた。
「それでも……因縁、というものでしょう」
彼の声が、少しだけ低くなる。
「マヌエル・アルグレ像の下で、瀕死のオリンさんを保護できたのは」
ハニスは胸の奥で、静かに何かが軋むのを感じた。
「ロン・シンファー君。
君が彼の偉業を継ぐと聞いて、嬉しい限りだ」
一瞬、亡き友の面影が脳裏をよぎる。
「アポリアナも、きっと喜んでいるだろう。
――イフニアでの親友の息子と、こんな縁で会うとはな」
そして、表情を引き締める。
「オリンのメモから察するに、君もコンシューアム員だな。
それにしても……どうやってネオ・エーテルに潜入できた?」
ハニスの声は、低く鋭くなった。
「今では、アポリアナの父が発明した精神雑音発生装置で、コンシューアム員は完全に排除されているはずだ。
それなのに、君はこの博物館の中枢に勤めている」
ロンは、まるで当然のことを語るように答えた。
「日進月歩、というやつです」
その言葉に、驕りはなかった。
「父は、コンシューアムの科学技術担当でした。
遮断装置を、さらに遮断する技術を生み出していた。
僕は、それを応用しただけです」
静かな誇りが、言葉の底に滲む。
「イフニア大学で、超高度データチップ化の博士課程を修了しています。
最近のネオ・エーテル技術は停滞気味でしたから……格好の就職先でした」
ハニスは、短く息を吐いた。
「では、君の潜入目的は?」
ロンの視線が、博物館の奥――アーカイヴ中枢へと向けられる。
「コンシューアムでは、反エムーが頻繁に表面化しています」
淡々とした口調。しかし、その言葉は重かった。
「第一調律師の指令は二つ。
一つは、その動向の調査。
もう一つは――」
わずかな間。
「アーカイヴを、我らの最終目標へと、背後から誘導することです」
ハニスの眉が、わずかに動く。
「今こそ、反クォンタム律が重視されるべきだと」
沈黙。
ハニスは、しばらく何も言えなかった。
「……そこまで進んでいたとはな」
低く、独白のように呟く。
「俺は、君たちの感応力を、甘く見ていたのかもしれん」
ロンは、首を横に振った。
「ですが、第一調律師は言っています。
第二コーデックスは、あくまで補助であるべきだと」
そして、核心に触れる。
「感応力を凌ぐ能力がある、とも」
ハニスは、即座に問い返した。
「それは、なんだ?」
「無謬の直感力です」
その言葉は、重く、静かに落ちた。
「……無謬の直感力、だと?」
「生命体の根源とも言われています。
そして、それは稀に、第一コーデックスから生まれる」
ロンの声に、わずかな羨望が混じる。
「この点では……我々は劣るのです。
天は二物を与えず、ですね」
ハニスは、目を閉じた。
理性でも、感応でもない。
それを超える“何か”。
「……では」
ゆっくりと、問いを投げる。
「その最終目標を、どうお膳立てするつもりだ?
ロン・シンファー君。君の方策とは?」
ロンは、静かに微笑んだ。
その笑みが、希望なのか、破局への序章なのか――
ハニスには、まだ判別できなかった。
つづく。

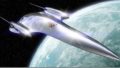
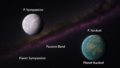
コメント